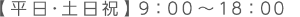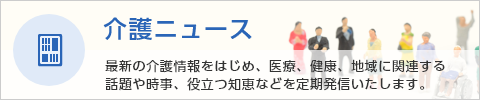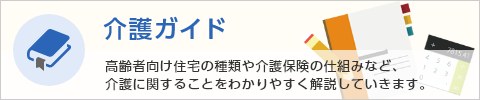グループホームとは?介護施設の特徴や費用、入居条件と選び方を解説
認知症の高齢者の方が、介護職員のサポートを受けながら、少人数かつアットホームな雰囲気で共同生活を送るのが「グループホーム(認知症対応型共同生活介護)」です。
| 目次 |
|---|
条件に合う施設の資料をまとめてお送りします
グループホームとは?
この章では、グループホームの特徴や役割、目的を説明します。
まずは「グループホームとは何か?」を理解していきましょう。
● グループホームは「認知症高齢者のための介護施設」
グループホームは、認知症対応型共同生活介護とも言い、認知症と診断された高齢者を対象として少人数で共同生活を送ることができる介護施設です。
認知症高齢者(以下「利用者」)に対して、住み慣れた地域で、家庭的な環境のもと、入浴や排せつ、食事等の日常の生活のお世話や機能訓練を行うことにより、利用者が持っている能力に応じて可能な限り、自立した生活を送ることができるよう支援することが目的です。
グループホームでは、5~9人を1ユニットとして小規模な共同生活を送ります(原則、1施設最大2ユニット)。
認知症の方は大勢での共同生活では落ち着いた暮らしができません。
グループホームは、利用者を少人数かつ見慣れたメンバーに限定することで、アットホームな雰囲気を作り、穏やかな生活が送れるようにしているのです。
● グループホームの特徴
グループホームの特徴をもう少し詳しく見ていきましょう。
- ・居住環境
個室が基本。部屋の床面積は収納設備等を除いて7.43㎡以上と定められています。
生活する部屋(個室)のほかに、利用者同士が交流できる共有スペースがあります。 - ・介護体制
日中は常勤換算方法で利用者3人に1人、夜間はユニットごとに1人と定められています。
「できることは自分で」が基本的なスタンスで、介護職員はサポートに重点を置きます。 - ・医療体制
緊急時の連絡先として協力医療機関と提携していますが、看護師配置は義務付けられていません。
日常的な医療ケアが必要な方は入居が難しいのが現状です。
昨今は医療ニーズにこたえて、医療連携体制加算を取得する施設も増えてきています。 - ・入居費用
0円~数百万円。施設や利用者の状況により異なります。
- ・月額費用
一般的に10~20万円程度ですが、施設や利用者の状況により異なります。
月額費用には、住居・管理費、食費、介護サービス費、その他(消耗品費・医療費等)が含まれます。
● グループホームのメリット・デメリット
グループホームのメリットとデメリットについて解説します。
グループホームのどんな点が優れていて、どんな点に注意が必要なのかをしっかり確認しましょう。
メリット
グループホームは、認知症ケアに特化した介護施設です。
入居する本人は、残存能力を活用して、家事を分担したりレクリエーションをしたりすることで認知症の改善や進行緩和を目指すことができます。
小規模な共同生活のため、少人数で落ち着いた生活を送ることができるのも大きなメリットといえます。
ご家族にとっては、認知症ケアの専門スタッフが対応してくれるため安心してご家族の介護を任せることができます。
デメリット
認知用ケアに特化しているため、注意しておきたいこともあります。
- ・通院時やトラブルがあると家族の協力が必要になることが多い
- ・医療依存度が高まると退所しなければならないことがある
- ・施設の絶対数が少ない上に、長期入所が可能なので、待機期間が長い
グループホームは、利用者が今できることを行いながら生活する施設です。
日常の家事なども他の利用者と分担して行ったり、スタッフにサポートされながら一緒に行ったりすることで、生活そのものが認知症のリハビリにつながります。
【グループホームまとめ】
| グループホームとは? |
|
|---|
あんしん相談窓口では、お身体状況により医療依存度が高まり転居が必要な場合や、待機期間が長く待ちきれない場合は、お客様のご状況に合わせて別の施設を提案することも可能です。
シニアのあんしん相談室は、グループホームを選ぶところから入居までサポートいたします。
まずはお近くのグループホームを調べてみましょう。
グループホーム入居時の費用や月額料金
入居を検討するなかで、気になるのは費用面ですよね。
グループホームの費用について、入居時と月々に必要な費用をそれぞれ詳しく見ていきましょう。
● 入居時に必要な費用
グループホームに入居するときにかかる初期費用は施設によって異なります。
初期費用として必要なのは、入居一時金や保証金です。
入居一時金は、施設を利用する権利を得るための費用で、基本的には家賃相当額の前払いとお考え下さい。
保証金は、一般的に賃貸でいうと「敷金」にあたるお金です。
グループホームへの入居に必要な初期費用は、有料老人ホームより金額が抑えられているのが一般的ですが、数百万円程度の金額になることもあります。
施設によっては月払いプランを用意し、初期費用がかからないケースもあります。
払った入居一時金や保証金、退去時はどうなる?
入居一時金として払った場合、施設により定められた償却期間と償却率をもとに計算され、未償却分が返還金として戻ります。償却期間を過ぎている場合は、返還金はありません。
保証金として払った場合は、退去する際に居室内の清掃や修繕などに利用されます。残金は基本的に返却されます。
● 月額料金
月額費用として必要になるのは、家賃、共益費、食費、水道光熱費、その他の生活費に加えて、介護サービス費(認知症対応型共同生活介護の自己負担分)です。
それぞれの費用の相場は下記のようになります。
| 家賃・管理費 | 約60,000~100,000円 |
|---|---|
| 食費 | 約30,000~60,000円 |
| その他の生活費 | 約5,000~10,000円 |
| 介護サービス費 | 【1割負担】約10,000~28,000円 【2割負担】約20,000~56,000円 【3割負担】約30,000~84,000円 |
施設によって特に大きく変わるのは、家賃です。家賃は、施設がある地域や設備の充実度、居室の大きさなどによって変わり、一般的には都市部のほうが地方よりも高い傾向があります。
その他の生活費としては、おむつ代などの消耗品費、理美容代、生活支援サービス費などの項目が含まれています。
介護サービス費は、利用者の要介護度、ユニット数に応じた「基本サービス費」と、施設の設備や対応するサービスに応じて発生する「サービス加算」で構成されます。
介護サービス費は、介護保険の適用を受け、自己負担は1割(収入に応じて2~3割)で利用できます。
基本サービス費は要介護度によって異なり、要介護度が高くなるほど費用が高く設定されています。グループホームでは1施設にいくつユニットがあるかによっても介護サービス費は異なり、1つよりも2つあるほうが、介護サービス費は下がります。
サービス加算は、施設によってどんな項目で加算されているかは異なります。
加算があるほど、充実した介護を受けられることにはなりますが、積もり積もると月額の費用の負担も大きくなります。入居を考えているグループホームが加算対象としている項目の内容を見ると、どんなサービスが受けられるかの手がかりにもなりますよ。
● 介護保険の自己負担額
グループホームは介護保険の地域密着型サービスに属するので、介護サービスによける費用は介護保険が適用されています。
グループホームに入居した場合の料金は要介護度ごとに決められた額を支払います。
下記は要介護度別のグループホームの介護保険サービス料の自己負担額です。
| 1ユニット 自己負担額30日(1割) |
2ユニット 自己負担額30日(1割) |
|
|---|---|---|
| 要介護1 | 2万2830円 | 2万2470円 |
| 要介護2 | 2万3910円 | 2万3520円 |
| 要介護3 | 2万4600円 | 2万4240円 |
| 要介護4 | 2万5110円 | 2万4720円 |
| 要介護5 | 2万5620円 | 2万5200円 |
グループホームは、高額介護サービス費の対象です。
介護サービス費として支払った自己負担額の1カ月累計が定められた上限額を超える場合は、市区町村から高額介護サービス費の支給を受けることができます。
● 費用に関するよくある質問
Q. グループホームに年金の範囲内で入ることはできる?
年金だけで入ることができる施設もありますが、選択肢は少なくなります。
立地により金額に差は出ますが、グループホームの入居一時金は0円~数百万円、月額費用は10~20万円程度です。
Q. グループホームは生活保護を受けていても入ることはできる?
生活保護の扶助で家賃や生活費をまかなうことができれば、生活保護を受けていても入居することは可能です。ただし、生活保護を受けている人を受け入れていなかったり、人数を制限していたりする施設もあります。実際に探す場合には、生活保護を受けていても入居ができるかどうかを施設側にきちんと確認しましょう。
Q. 世帯分離で介護費用が節約できるって本当?
介護サービスを利用する際、費用の一部は利用者の自己負担です。負担額は「高額介護サービス費制度」で上限が定められていて、限度額を超えた場合には申請すれば払い戻しができます。
自己負担限度額は、世帯の所得によって決まります。生計を共にしていない親族と同一世帯になっている場合、世帯収入が多くなり、自己負担限度額が引きあがりますが、世帯分離をすることで限度額が下がり、介護費用の節約につながります。
世帯分離はデメリットもあります。人によっては世帯分離をすると負担額が増えてしまう場合もあるので注意が必要です。
確認しておきたい5つの入居基準
グループホームに入居するためにはいくつかの基準があります。
入居を検討する前に、基準を満たしているかを確認しておきましょう。
1.認知症の診断は受けていますか?
グループホームは、認知症の診断を受けていないと入居することはできません。入居にあたっては、医師の診断書や診療情報提供書など、認知症であることを確認できる書類の用意が必要です。
2.要支援2以上の認定を受けていますか?
グループホームは、要支援2、要介護1~5の認定を受けている方が対象となります。
介護保険制度を利用してのサービスになるので、利用者の負担は原則1割になります。
3.施設と同じ市区町村に住民票がありますか?
2006年の介護保険改正後からグループホームは地域密着型サービスに位置付けられました。
そのため、グループホームを利用できるのは、その地域に住んでいる人だけです。入居するには、その地域に住んでいることの証明として住民票が必ず必要になります。
4.年齢は65歳以上ですか?
グループホームに入居できるのは原則65歳以上の方です。
施設によっては、65歳未満の方で初老期認知症や若年性認知症と診断された方は利用可能な場合もあります。
5.集団生活に支障はありませんか?
グループホームでは、少人数のグループで共同生活を送ります。集団生活を送ることに支障があったり、自傷他害の恐れがあったりすると入居できない場合も多くあります。
判断基準は施設によって異なりますので、事前に確認しておくと安心です。
入居前に知っておきたい注意点
ループホームは有料老人ホームやサービス付高齢者向け住宅とは少し性質が異なります。
グループホーム特有の注意点を理解しておくようにしましょう。
● 入居にはその地域の住民票が必要
グループホームは「地域密着型サービス」なので、その地域に住んでいる人のみ利用ができます。その証明として住民票が必要です。
今住んでいる地域にあるグループホームに入居する場合は特に心配はいりませんが、例えば別の場所で暮らす親を呼び寄せて、子の近くにあるグループホームへ入居してもらおうとしても、すぐに入居することはできません。自治体によっては、住民票を移してから一定期間(原則3カ月以上)を経過しないと申込みができないので、入居を検討している場合は、早い段階でその施設や役所に問い合わせることをおすすめします。
● 住所地特例は適用されない
「住所地特例制度」とは、老人ホームに転居して別の地域に住民票を移した後も、以前住んでいた市区町村に保険料を支払い、介護保険の給付を受けることができる制度で、特定の自治体に保険料の負担が集中することを防ぐためにつくられました。
利用者としては、介護保険料が転居後に高くなってしまう場合でも、住所地特例制度の対象であれば介護保険料や給付が現在と変わらないというメリットがあります。
地域密着型サービスであるグループホームは、住所地特例の対象外のため注意が必要です。
● 医療的ケアが必要になると退去が必要なことも。
グループホームでは、万が一に備えて提携医療機関が定められていますが、看護職員の配置に関する基準はないため、医療ケアは弱いという側面があります。医療依存度が高まり、日常的に医療ケアが必要になった場合には退去が必要なこともあります。
定員数と施設数から見た入居難易度
当然ながら介護施設は部屋に空きがなければ入居はできません。それはグループホームも然りです。
ここでは、グループホームの施設数や定員数の観点から入居難易度を考えてみましょう。
● 施設数は増えている?
平成12年(2000年)で675件だったグループホームは、平成29年(2017年)には13,114件と約19倍に事業所数を伸ばしています。
今後のさらなる65歳以上の高齢者数の増加、特に介護を受ける可能性の高い75歳以上の高齢者数が急速に増えることに備えて、現在国では在宅・施設サービス等の整備の充実・加速化が重点的な取組の一つとされています。
2015年度から2020年代初頭にかけて、従来の計画に基づくと約38万人分増でしたが、さらに約10万人分増の在宅・施設サービスの前倒し・上乗せ整備が計画されています。
認知症グループホームは、約10万人増の対象として想定されている在宅・施設サービスの一つなので、高齢者増加に伴い、今後しばらくは増加するものと考えられます。
● 少人数での共同生活が基本のため定員数は少ない
施設数の増加に伴い、グループホームの定員数は平成12年時点の5450人から平成28年には19万3400人まで伸びています。
しかし、グループホームには1施設に原則、最大18人(1ユニットあたり5~9人、1つの施設で最大2ユニット)しか入居できないという制限があります。そのため、実は施設数が増えている割に、定員数の伸びは他の種類の施設と比較して少ないのです。平成28年で定員が57万8900人の特別養護老人ホームや45万7918人の有料老人ホームと比べると、定員数が少ないのが現状です。
● グループホームの入居難易度
グループホームは、
・住んでいる地域のグループホームにしか入居できないので選択肢が狭い
・定員数が他の施設と比べて少ない
という理由で入居難易度は比較的高めです。
空きがあることも少ないので、数ヶ月から数年の入居待ちになる可能性もあります。
グループホームに空きがなく入居が難しい場合は、認知症ケアがしっかりしている有料老人ホームに入居するのも選択肢の一つですよ。
グループホームで受けられるサービス
● 「できることは自分で」が基本
グループホームは、「できることは自分で」が基本的なスタンスです。
入居者ができるだけ自立した生活を送ることができるように介護職員はサポートに重点を置いています。入居条件が要支援2以上で認知症と診断された方となっていますが、身体は比較的お元気な方が多く、寝たきりなどの方は少ないのが特徴です。
● 「認知症ケア」とは?
認知症ケアにおける考え方の一つに「パーソン・センタード・ケア」というものがあります。
これは、1980年代末にイギリスの臨床心理学者のトム・キットウッド氏によって提唱された、『認知症を持つ人を一人の”人”として尊重し、その人の立場に立って行う』というものです。
認知症になっても、すべてが分からなくなったり、何もできなくなったりするわけではありません。
認知症を持つ人の声に耳を傾け、一人の人として尊重するケアは、認知症の回復をもたらし、重度化していた状態から、その方本来の姿を引きだすことを可能にするとも言われています。
パーソン・センタード・ケアでは、認知症ケアでまず大切なことは認知症を理解することと心理的ニーズを満たすことといわれています。
認知症には、脳の障害・身体の状態・生活歴・性格・取り囲む環境や社会という5つの要素が相互作用で起こり状態が左右されます。これらを手掛かりに一人一人の適切なケアが何かを見つけていきます。
また、心理的ニーズには、愛を中心として自分らしさ・結びつき・たずさわること・ともにあること・くつろぎという要素が並びます。
例えば、思い出写真を部屋に飾る、愛着のあるものを身の回りに置く、家事をする、地域の人との交流をする、なじみの場所で生活をする、など心理的ニーズを満たすようなケアがグループホームではなされています。
● 介護体制
食事の提供、掃除や洗濯、見守り・生活相談、食事介助、入浴介助、排泄介助、着替え介助、レクリエーションなどはほとんどの施設が提供し、十分なサービスを受けられます。
人員配置は、介護付き有料老人ホームと同じ基準である介護職員が常勤換算で3:1以上(入居者3名に対して介護職員が1名以上いる)が義務付けられています。
● 医療対応は施設によってまちまち
グループホームでの医療対応は基本的に手厚くはありません。
というのも、グループホームでは医師や看護職員の常駐は義務付けられておらず、日常的な医療ケアが必要な方は入居が難しいのが現状です。
入居後に身体の状況が悪化して、医療依存度が高まってしまうと退去せざるを得ないケースもあります。
最近では医療ニーズの高まりから、看護師の配置や、病院・診療所・訪問看護ステーションと連携したりするなどの医療連携体制を整えているグループホームも増えてきています。
また、看取りまで対応できるかどうかも施設により異なります。
施設によって、医療連携体制や看取り対応など医療対応の充実度は異なります。
施設のパンフレットに書かれている介護サービス費加算項目に「看取り加算」や「医療連携体制加算」などがあるかを確認してみると、どのようなサービスが受けられるかの手がかりになります。
詳しいサービス内容は直接施設に確認してみましょう。
● レクリエーション
レクリエーションは、有料老人ホームと同じようなものが多いですが、特に手先を使ったものや音楽療法・回想療法、アニマルセラピーなど認知症に効果があるものが中心に構成されています。
施設内では、スタッフと一緒に買い物や食事の準備、清掃などの家事を行ったりするので、生活すること自体がリハビリにもなります。これは認知症の進行緩和を目的にしています。
● 個別対応はできる?
小規模な施設なので、スタッフも少なく、個別対応は難しいというのが実情です。
● 施設によって受けられるサービスは異なる
施設によって、受けられるサービスは異なります。
医療連携体制や看取り対応などは、施設のパンフレットに書かれている介護サービス費加算項目に「看取り加算」や「医療連携体制加算」などがあるかを確認してみると、どのようなサービスが受けられるかの手がかりになります。詳しいサービス内容は直接施設に確認してみましょう。
グループホームの退去基準と転居先
● グループホームの退去基準
退去しなければならない基準はグループホームによって異なりますが、「入居対象」の条件から外れてしまった場合には退去勧告をされる場合があります。代表的な理由には以下のようなものがあります。
- ・医療依存度が高くなった場合(病気の治療が必要な場合)
- ・認知症状が著しく共同生活を送ることが困難となった場合
- ・暴力行為、自傷行為など他の入居者に迷惑をかけてしまう場合
- ・継続して一定期間以上の入院治療が必要となった場合
- ・月額費用など必要な料金を滞納し続けた場合
グループホームでの医療ニーズに対応できるよう、2018年の制度改正で、医療連携体制加算が加わりました。これは、利用者の状態に応じた医療ニーズに対応できるように看護体制を整備している事業所を評価する加算です。
このような制度ができても、すぐに全てのグループホームで医療ニーズに対応することは難しいのが現状。検討しているグループホームでの退去が必要となる基準は事前に確認しておくようにしましょう。
● 退去後の行先はどうする?
グループホーム退去後は、病院、介護老人保健施設(老健)、特別養護老人ホーム(特養)、民間の有料老人ホームに移ることが多いとされています。
介護老人保健施設は基本的に3~6カ月しか利用することはできません。
また、特別養護老人ホームは費用を抑えることはできますが、要介護度3以上でなければ入居することはできません。
ご自宅に戻ることが難しいようであれば、民間の運営する介護付き有料老人ホームに入居するのも選択肢の一つす。介護や医療の体制は、施設によって異なるので入居を検討しているご本人のお身体状態が受け入れ可能かどうかを事前に確認する必要があります。
グループホームと他施設の違い
グループホームは他の施設とどう違うのかに注目してみましょう。
ここでは特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護付き有料老人ホームと比較してみます。
| グループホーム | 特別養護老人ホーム(特養) | 介護老人保健施設(老健) | 介護付有料老人ホーム | |
|---|---|---|---|---|
| 入居条件 |
・認知症の診断を受けている ・要支援2以上 ・施設のある地域の住民票が必要 |
・要介護3以上 | 要介護1以上 | 施設により異なる |
| 介護 | △ | ○ | ○ | ○ |
| 医療 | △ | △ | ○ | ○ |
| 月額費用 | 13~20万円 | 6~15万円 | 8~20万円 | 15~35万円 |
| 認知症受け入れ | ○ (認知症ケアに特化) | ○ | ○ | △ (施設による) |
| 終の棲家になるか | △ (状態による) | ○ | × | ○ |
| 運営母体 | 民間 | 公的 | 公的 | 民間 |
● 特別養護老人ホーム(特養)との違い
特別養護老人ホーム(特養)は地方自治体や社会福祉法人が運営する公的の施設で、原則65歳以上で要介護3以上という入所条件があります。
グループホームとの大きな違いは、介護面。寝たきりなどで常時介護が必要な方も入所することができ、食事や入浴、排せつなど生活全般にわたる手厚い介護を24時間受けることができます。
● 介護老人保健施設(老健)との違い
介護老人保健施設(老健)は、病気などで入院した後に自宅での生活が難しくなってしまった高齢者に対して、看護や介護、医療ケアやリハビリなど日常生活のサポートを提供する施設です。
グループホームとの大きな違いは、充実した医療ケアが受けられるという点ですが、リハビリを通じて自宅での生活に復帰してもらうことを目的としているため、長期利用はできません。
● 有料老人ホームとの違い
有料老人ホームには、介護付き有料老人ホームや住宅型有料老人ホーム、健康型有料老人ホームがあります。介護付き有料老人ホームでは、食事の提供や掃除・洗濯など生活援助から、身体介助まで様々な介護サービスが提供されます。この介護の手厚さがグループホームとの大きな違いといえます。
介護付き有料老人ホームの中には、認知症の方を受け入れている施設もありますが、グループホームのように少人数での生活だったり、スタッフが認知症ケア専門だったりなど、認知症ケアに特化した施設ではありません。
良いグループホームの見分け方
グループホームといっても、一施設一施設に特色があります。
多くのご相談を受けてきたあんしん相談室の入居相談員の目線でのグループホームを選ぶポイントや見学時に見るべきポイントを紹介します。
● グループホームの選び方
数あるグループホームの中から絞り込むときに、どのような観点で選ぶべきか。
今回は3つのポイントを紹介します。
- 1.エリア
ループホームの場合は、大前提として住民票のあるエリアの中で探さなければいけません。
そのエリアの中で通いやすい場所に絞り込むと良いでしょう。交通手段が車か電車かによって、通いやすさは異なってきます。電車の場合は、電車に乗っている時間はもちろんのこと、乗り換えの少なさも考慮しておくと良いでしょう。 - 2.予算
選ぶ上ではずすことができないのは、予算内かどうかです。
入居時の費用や月々の費用が払える範囲なのかどうかを確認しましょう。 - 3.入居される方の状況
グループホームは、医師や看護職員の常駐は義務付けられていないため、基本的には医療対応が難しいものですが、中には医療ニーズに対応するために医療体制を整えているグループホームもあります。
医療対応が必要になる可能性が高い場合、現状でも医療対応が少なからず必要な場合には、医療対応が可能かどうかを確認しておくと安心です。
・医療対応実績はあるか
・24時間看護師常駐である場合、必要な医療措置の対応が可能かどうか
・往診医には、内科ではなく精神科や老年内科が入っているか
といった点に注目すると良いでしょう。
● グループホーム見学時に見るべきポイント
グループホームに足を運んで見学を行うときには、パンフレットなどでは分からない情報を積極的に収集することが大切です。特に見るべきポイントを5つ紹介します。
- 1.スタッフの人数
ループホームでの人員配置基準は、ユニットごとに日中の時間帯に常勤換算で利用者3人に介護職員が1人と定められています。
グループホームでは、入居者ができないことをサポートするという考え方が基本になっているので、どうしても人手が必要になります。入居者が主体でスタッフはサポートという体制が整っているかどうかを確認しておくと良いでしょう。 - 2.どんなことを一緒にやっているか
料理をしたり、洗濯物を畳んだり、レクリエーションをしたりなど、スタッフと入居者が一緒に何をやっているかを確認しましょう。
グループホームは、日常生活の動作が機能訓練の役割を果たしている面もあるため、一緒にやっていることが多い方が望ましいです。 - 3.レクリエーションの内容
簡単な計算や言葉を使ったゲーム、パズルなど脳を使って楽しむレクリエーションは認知症予防にもつながります。レクリエーションには、体を動かすものや手先を使うもの、音楽と使うレクなど様々ですが、認知症予防につながるようなレクリエーションが組み込まれているかを確認すると良いでしょう。
また、レクリエーションの際に、興味がわくような声かけがされていて、入居者が参加しているかどうかもチェックしておくと安心です。 - 4.入居者の表情
実際に施設内で暮らしている方の表情を確認しましょう。「笑顔」の表情が必ずしも良いとは限りません。私たちも日常生活の中では常に笑顔でないように、入居者もそこで生活をしているため、笑顔以外の怒り、悲しみなど様々な表情があります。
入居者の表情が、作られたようなものではなく自然なものかどうかに注目しましょう。
また、一人ぼっちになっている人がいないか、も注目ポイントです。 - 5.どんな人が入居しているか
グループホームは、他の介護施設よりも少人数で共同生活を送るというのが一つの特徴です。
そのため、他の入居者との関わりも必然的に強くなるため、男女比率、年齢、雰囲気などどんな人が入居しているかを確認して、馴染めそうかどうかを考えてみましょう。
● ショートステイや体験入居は?
グループホームでも基本的には空室があればショートステイ(短期入居)や体験入居は可能です。
ショートステイは介護サービスの一環としての利用のため、ケアプランの作成が必要です。ショートステイは、一時的に在宅で介護ができなかったときはもちろん、レスパイトケア(リフレッシュや休息をとる介護者のためのケア)の一つとしても利用できます。1日単位で、最大30日間の利用が可能です。
体験入居は、介護保険の適用外になりますが、入居しても問題なく生活できるかを確認するためにはおすすめです。
いずれにしても、対象のグループホームに空室がなければショートステイや体験入居はできないため、事前に空き状況を確認しておくようにしましょう。
● 入居までの流れ
- 1.グループホームを選び、比較検討
グループホームは、その地域の住民票を持っていなければ入ることができません。
施設と住民票のエリアが異なる場合は、転居と同時に住民票を移せば入居が可能なのか、もしくは住民票を移してから一定期間は入居できないのかを確認しましょう。 - 2.見学
興味のある施設が見つかったら見学に行きましょう。
- 3.入居申込み
費用や条件など問題がなければ申し込み手続きに進みます。この時点では「仮押さえ」状態。
仮押さえの間に必要な書類の準備などを行います。 - 4.書類の提出
利用申込書、健康診断書、診断情報提供書(紹介状)、印鑑、各種保険証が必要です。 グループホームは、認知症であることの診断書も必要になります。
その他、施設によっては戸籍謄本や印鑑証明などが必要になる場合もあります。 - 5.本人面談
施設側が入居者本人の健康状態を確認します。
- 6.入居審査
提出書類をもとに入居審査を行います。
- 7.契約・入居日確定
面談や審査に問題なければ契約に進みます。
- 8.入居
新しい環境での生活がスタートします。
入居時に必要なものは事前に施設に確認しておくと安心です。
一般的には入居まで約2~3カ月が必要です。空室がなければ、空室が出るまで待たなくてはいけません。 入居を検討している方は、余裕をもって施設選びから始めてみましょう。
● 周辺のグループホームを探してみよう
シニアのあんしん相談室では、介護施設選びから入居まで専門の相談員がしっかりサポートいたします。
提携している全国のグループホームからお客様に合った施設を見つけることができます。お住まいの地域のグループホームを探してみましょう。
条件に合う施設の資料をまとめてお送りします
グループホームのまとめ
| 年齢 | 65歳以上 | 認知症 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 介護レベル | 要支援2~要介護5 | 共同生活 | 必須 |
| 入居・入所時費用 | 0円~数百万円 | 月額費用 | 約10万円~20万円 |
|---|
| 介護サービス費 | 【1割負担】 約10,000円~28,000円 【2割負担】 約20,000円~58,000円 |
住居・管理費 | 約60,000円~10万円 |
|---|---|---|---|
| 食費 | 約30,000円~60,000円 | その他 | 約5,000~10,000円 |
| 介護職員 | 3:1以上(常勤) | 看護職員 | 施設によって異なる |
|---|---|---|---|
| 医師 | 勤務なし | その他 | ― |
| 食事提供 | ◎ | 掃除・洗濯 | ◎ |
|---|---|---|---|
| 見守り・生活相談 | ◎ | 買い物代行 | ○ |
| 食事介助 | ◎ | 入浴介助 | ◎ |
| 排泄介助 | ◎ | 着替え介助 | ◎ |
| 機能訓練(リハビリ) | △ | レクリエーション | ◎ |
| 医療ケア | △ | 服薬管理 | ○ |
|---|---|---|---|
| 医療機関との連携 | ○ | 通院時の送迎 | △ |
| 居室の種類 | 個室 | 居室の広さ | 7.43平米~ |
|---|---|---|---|
| 浴室の場所 | 共有 | 浴室設備 | 通常浴室/機械浴 |
| トイレ | 共有 | キッチン | 共有 |
| 食堂・リビング | 共有 | 洗濯室 | あり |
| 娯楽設備 | 施設によって異なる | 理美容設備 | あり |
| 機能訓練室 | あり | 健康管理・相談室 | あり |
|---|
条件に合う施設の資料をまとめてお送りします
老人ホーム・介護施設の比較一覧
介護でお悩みの方なら「介護ガイド」。各高齢者向け住宅の説明や介護保険制度のこと、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の入居までの段取りガイドなどをご紹介します。
| 老人ホーム・介護施設の種類 | 費用の目安 | 入居条件 | 終の すみか |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 月額 | 自立 | 要支援 | 要介護 | 認知症 | |||
| 民間型 | 有料老人ホーム | 0~数千万円 | 15万~35万円 | |||||
| 介護付き有料老人ホーム | 0~数千万円 | 15万~35万円 | ||||||
| 住宅型有料老人ホーム | 0~数千万円 | 15万~35万円 | ||||||
| サービス付き高齢者向け住宅 | 大半が敷金のみ |
13万~25万円
※食事など除く |
||||||
| グループホーム | 0~30万円 | 13万~20万円 | ||||||
| シニア向け分譲マンション | 数千万~1億円 |
5万~20万円
※食事など除く |
||||||
| 公共型 | 特別養護老人ホーム | なし | 6万~15万円 | |||||
| 介護老人保健施設(老健) | なし | 8万~20万円 | ||||||
| 介護医療院 | なし | 8万~20万円 | ||||||
| ケアハウス(軽費老人ホーム) | 0~数百万円 | 8万~15万円 | ||||||

記事監修:老人ホーム入居相談員(介護福祉士、社会福祉士、ホームヘルパー2級、宅地建物取引士、認知症サポーター)
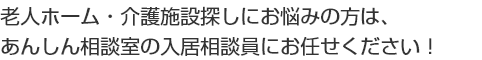 0120-371-652
0120-371-652