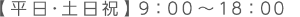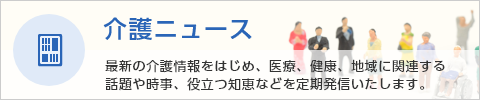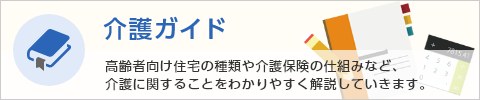老人ホーム入居契約の注意点|重要事項説明書のチェックポイントも紹介!
入居する老人ホームを決めた後、不安なことや疑問に感じることがある場合は、施設側に質問するなど、納得した上で契約に進むことが大切です。また、老人ホームの入居契約を結ぶ前には、重要事項説明書の説明が行われるため、内容をきちんと理解することが入居後のトラブルを防ぐためにも重要です。ここでは、老人ホームの入居契約前の注意点や、重要事項説明書で主にチェックすべきポイントなどについて解説します。
老人ホーム入居契約前の注意点

老人ホームへの見学や体験入居などを済ませて入居する施設が決定したら、いよいよ入居契約に進むこととなります。ただし、老人ホームの入居契約を行った後で後悔したり、トラブルになったりすることを避けるためには、以下の2つの注意点を押さえておくと良いでしょう。
- ・入居する本人の意思も大事
- ・費用についてのトラブル
■ 入居する本人の意思も大事
老人ホームの入居契約の前には、必ず入居する本人の意思を、改めて確認しておくことが大切です。本人が不安に感じていることがあるにも関わらず、それを解決しないまま契約を進めてしまうと、契約後に考え直してキャンセルすることになり、キャンセル料が発生してしまうケースがあります。あるいは、短期間で退去することになって新しい施設を探すとなると、労力も費用負担もかかります。
そのため、本人と家族がよく話し合ったり、友人に相談したりするなど、本人の気持ちを整理し、入居に対する考えを再確認する時間を取ることが必要です。もし、施設側から契約をせかされたとしても、早急に手続きを行うことを避け、本人や家族が納得いくまで施設と話し合うようにしましょう。
■ 費用についてのトラブル
老人ホームの入居契約の前には、費用について後々にトラブルが起こることを避けるために、事前によく確認しておくことが大切です。なぜなら、老人ホームの契約後に費用を巡るトラブルは、実際にとても多いからです。
特に、費用に関するトラブルとして目立つのは、早期に退去することになった場合の入居一時金から減価償却費や原状回復費を引いた「返還額」に関することです。多くの有料老人ホームでは、入居時の初期費用として入居一時金が発生します。このほか、家事代行サービスやレクリエーションの費用が月額費用に含まれていると考えていたのに、オプション費用として別途かかって想定外の出費がかさむといったケースも見受けられます。
こうした費用に関するトラブルを避けるためにも、契約前には、重要事項説明書の内容をあらかじめ確認しておくことが望ましいです。
重要事項説明書とは
老人ホームの重要事項説明書とは、運営する法人の事業主体概要、建物概要、サービスの内容、職員体制、利用料金などが記載された書類のことです。介護付き有料老人ホームや住宅型有料老人ホームなどの有料老人ホームは、「老人福祉法29条」と「老人福祉法施行規則20条の5」で、重要事項説明書の届け出を都道府県に行うことが義務付けられています。また、契約を行う際には、重要事項説明書に基づいて説明を行うことも義務付けられています。
■ 重要事項説明書に記載されている内容
重要事項説明書に記載されている項目と主な内容をまとめてみました。
| 事業主体概要 | 事業主の名称、所在地、連絡先などの基本情報 |
|---|---|
| 有料老人ホーム事業の概要 | 施設の名称、所在地、管理者、連絡先、施設の種類、事業開始年月日 |
| 建物概要 | 敷地・建物の面積、建物の構造、所有関係、居室区分、居室数、居室面積、共用設備、消防用設備 |
| サービスの内容 | 運営方針、サービスの提供体制(各サービスについて施設による提供・外部委託など)、介護サービスの内容、医療連携、入居後の居室の変更、入居に関する要件、契約解除の条件、体験入居の内容 |
| 職員体制 | 職種ごとの常勤・非常勤の人数、介護職員と機能訓練指導員の有資格者の人数、夜勤帯の介護職員と看護職員の平均人数・最小時人数、特定施設入居者生活介護等の提供体制、職員の採用数・退職者数・経験年数などの状況 |
| 利用料金 | 権利形態(利用権方式・建物賃貸借方式・終身建物賃貸借方式)、利用料金の支払い方式、入院などによる不在時の利用料金の取り扱い、利用料金の改定のルール、利用料金のプラン、利用料金の算定の根拠(内訳)、前払い金がある場合の取り扱い |
| 入居者の状況 | 入居者の人数(性別・年齢別・要介護度別・入居期間別)、平均年齢や入居率など入居者の属性、前年度の退去者の状況 |
| 苦情・事故等に関する体制 | 入居者からの苦情に対応する窓口、損害賠償保険の加入の有無、利用者などの意見を把握する体制、第三者からの評価の実施状況 入居希望者への事前の情報開示 入居契約書のひな型・管理規程・事業収支計画書・財務諸表の開示状況 |
| その他 | 運営懇談会の実施の有無、提携ホームへの移行 |
重要事項説明書に記載されているのは、職員体制、利用料金、入居者の状況、サービスの内容などであり、契約前に知っておくべき施設についての情報が記載されています。
■ 重要事項説明書の確認が大切である理由
老人ホームへの入居契約を結ぶ前に、重要事項説明書の記載内容について確認し、分からない点がある場合は、施設側に質問しておくことが大切です。
重要事項説明書の記載内容を理解せずに契約すると、入居後にトラブルが発生したとき、施設側に「重要事項説明書に記載されている通りです」と説明されて、反論できないことも考えられます。また、料金プランの認識が誤っていると、月額費用に含まれていると思っていたものが含まれておらず、想定外の費用が請求され、資金計画が狂ってしまいます。あるいは、契約後に何かに気付いて解約すると、キャンセル料が発生したり、施設を探し直さなければならなかったりするなど、費用も手間もかかってしまいます。重要事項説明書に不明点があった場合は、必ず契約書に判を押す前に、施設側へと確認するようにしましょう。
重要事項説明書のチェックすべきポイント

では、重要事項説明書を読むときには、特にどのような点に注意すれば良いのでしょうか。以下、チェックすべきポイントを紹介します。
- ・入居金や利用料などの費用
- ・契約解除の決まり
- ・介護サービス
- ・医療体制
重要事項説明書のチェックは、入居契約前の最終確認として慎重に行い、不明点や疑問点を理解できるまで質問するなど、納得してから契約へと進みましょう。
■ 入居金や利用料などの費用
利用料金に関する項目では、入居一時金や月額の利用料などについて確認します。
入居一時金は、早期に退去した場合、どの程度のお金が戻ってくるのかを把握しておくために確認しておくべき項目です。まずは、初期償却率と償却期間を確認します。初期償却率は低い方が望ましく、「40%以内」に設定されているのが一般的です。償却期間は長い方が良く、一般的には「3~5年」とされています。
入居一時金などの前払い金を受領する老人ホームは、「老人福祉法29条第8項」において、3カ月以内に退去する場合の返還規定を設けることが義務付けられており、「90日ルール」と呼ばれています。これは、契約の解除や入居者の死亡によって入居契約が終了した場合、家賃やサービス提供費などの実費相当額を差し引いて返還するという規定です。
また、万が一、運営会社が倒産した場合に備えて、入居一時金などの前払い金の保全措置の有無や方法についても確認しておきましょう。
月額利用料は、家賃、管理費、食費などが含まれているもの、実費として別途請求されるものを確認しておくことが大切です。例えば、施設によって水道光熱費が含まれているケースと、別途請求となっているケースがあります。また、入院などの不在時に月額利用料の割引があるかどうかについてもトラブルになりやすいので、確認しておきましょう。
- ・入居一時金の償却方法
- ・3カ月以内の契約終了による返還金
- ・入居一時金の保全措置
- ・月額利用料に含まれているもの
- ・入院などによる不在時の費用
■ 契約解除の決まり
契約解除の決まりに関しては、サービスの内容の項目に記載があり、事業主側から契約解除を求められる退去要件について確認しておきます。入居者の重大な契約違反や社会通念上契約の維持が困難な場合といった記載があれば、具体的にどういったケースが該当するのかを確認しておくことが必要です。長期の入院などによって不在になると解約を求められるような場合は、契約解除となる期間について確認しておきます。
また、入居者の都合で解約する場合は、退去予告期間よりも短い期間で解約の意思を伝えると、退去予告期間までの費用が発生することとなります。
- ・退去要件
- ・入居者からの退去予告期間
■ 介護サービス
介護サービスに関しては、職員体制、サービスの内容、苦情・事故等に関する体制の項目を確認します。
職員体制では、職員数などを基に、介護が必要な入居者に対する職員の比率を確認します。比率の低い方が手厚い介護を受けられることが期待できます。夜間の体制では、介護職員に加えて看護職員も常駐していると安心です。また、職員の入れ替わりが多いと落ち着いて暮らしにくいことが考えられるため、前年度の採用人数と退職人数もチェックしておきましょう。
特定施設入居者介護の指定を受けている介護付き有料老人ホームなどの場合は、サービスの内容の項目に介護サービス内容の記載があり、各種加算給付の有無を確認できます。
万が一、入居後にトラブルが生じた場合に備えて、利用者からの苦情に対応する窓口の体制や、損害賠償責任保険の加入の有無などの項目についても確認しておくべきです。
- ・職員体制
- ・介護サービスの内容
- ・利用者からの苦情に対応する窓口
- ・損害賠償責任保険の加入の有無
■ 医療体制
医療体制は、サービスの内容の項目の医療連携の内容に記載があり、医療支援の体制や、日頃から診療を受けられる医療機関を確認しておきます。
医療支援の体制では、入退院時の付き添いや通院介助に対応しているかどうかも、チェックすべきポイントです。協力医療機関には、内科、外科のほか、整形外科、耳鼻科、眼科、皮膚科、歯科などが入っていると診療を受けやすく、安心です。
- ・医療支援の体制
- ・協力医療機関
契約のための必要書類
重要事項説明書を確認して問題なければ、入居契約のステップに進んでいきます。施設によって違いがありますが、一般的な老人ホームの入居契約のための必要書類としては、次のようなものが挙げられます。
- ・住民票(本人・連帯保証人や身元引受人)
- ・印鑑証明(本人・連帯保証人や身元引受人)
- ・健康診断書
- ・診療情報提供書
- ・看護サマリー(病院から入居するケース)
- ・介護保険証
- ・健康保険証
- ・運転免許証や健康保険証などの身分証明書(連帯保証人・身元引受人)
- ・連帯保証人・身元引受人
- ・印鑑(本人・連帯保証人や身元引受人)
まとめ
老人ホームと入居契約を結んだ後に、実際の契約内容との認識の違いから施設を退去することになってしまうと、金銭的にも精神的にも大きな負担となります。入居後のトラブルを避けるためには、重要事項説明書をよく読んだ上で、不明点や疑問点について施設側に確認することが大切です。施設の運営状況や重要事項説明書に記載された内容について、本人や家族が納得した上で入居契約へと進むようにしましょう。
入居までの手引き

現在の収入、将来の収入、保有している資産と照らし合せて資金計画を立てましょう。
詳細を見る 選び方・比較・検討
自分に合った介護施設の種類や資金計画のイメージができたら、実際に老人ホームを探してみましょう。
詳細を見る オンライン入居相談
パソコンもしくはスマートフォンから入居相談員に無料で老人ホーム探しについて相談できます
詳細を見る 見学のポイントと手順
老人ホームは入居者に合うかどうかが大切です。失敗しない老人ホームの探し方の流れや、選び方のポイントなどを紹介します。
詳細を見る 入居契約の注意点
見学・体験入居を済ませたら、いよいよ契約です。重要な項目や手続きに必要な書類をしっかり確認しましょう。
詳細を見る 退院後の施設探し
突然の入院時には退院後の生活を考えることが必要です。そんな時には「退院支援ハンドブック」をご活用ください。
詳細を見る 介護疲れの負担軽減方法
「介護疲れ」が、しばしば問題になることがあります。介護疲れを引き起こす要因や、軽減するための方法などについてご紹介します。
詳細を見る 転居の方法
老人ホームを転居したい理由、住み替えの方法、住み替える場合の注意点などを紹介
詳細を見る 親の老人ホーム入居
親が介護施設に入るときの手順や、入居を検討すべきタイミング、入居を嫌がる場合の対処方法を紹介します。
詳細を見る 介護保険とは
介護が必要な人を社会全体で支えるための介護保険制度。介護保険制度の仕組みや対象者、介護保険で利用できるサービスなどについて紹介します
詳細を見る 要介護認定とは
介護保険による介護サービスを利用するために、必要となるのが要介護認定です。要介護認定とは何か、基準や要介護と要支援の違いなどについて解説します。
詳細を見る 高齢者の一人暮らし
近年増加している高齢者の一人暮らし。高齢者の一人暮らしで起きる問題点や、家族ができること、活用できる支援サービスについて解説します。
詳細を見る 紹介センターの活用
希望条件に合った老人ホームを探すためには、老人ホームの紹介センターへの相談がおすすめです。
詳細を見る
記事監修:老人ホーム入居相談員(介護福祉士、社会福祉士、ホームヘルパー2級、宅地建物取引士、認知症サポーター)
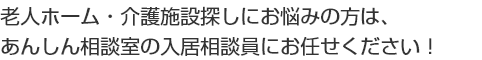 0120-371-652
0120-371-652