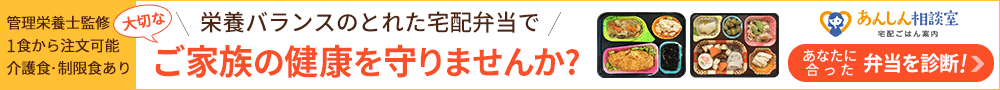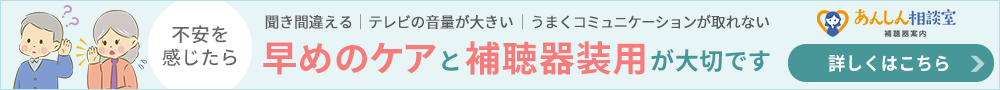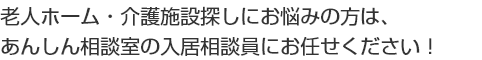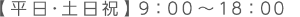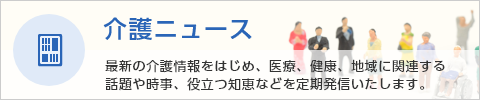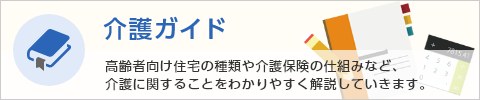認知症の方が食事しないのはなぜ? 食事拒否の原因と対応方法
2017.11.8

認知症が進行すると食事を拒否するようになることも珍しくありません。「なぜ食べてくれないの?」と悩みを抱えてしまう方も少なくないでしょう。
ここでは、介護をする方が知っておきたい、食事拒否の原因と対応方法についてご紹介します。
食事拒否の原因と対応方法
■食べ物だと認識していない
認知症が進行すると、食事を目の前に出されても食べ物と認識できていないことがあります。これは認知症の症状のひとつで“失認”というものです。 食べ物だと分かっていないため、手でいじったり放り投げたりしてしまいます。
≪対応方法≫
食事を提供する際に「美味しいごはんですよ」「好きな○○ですよ」などと声をかけましょう。目の前で食べて見せることで、食べ物だと認識してくれることもあります。
■食べ方が分からない・忘れてしまう
食べ物であることは分かるのに食べ方が分からなくなってしまうことがあります。これも認知症の症状のひとつで“失行”と言います。箸の持ち方や使い方、食べ物を口に運び噛んで飲み込むといったごく自然に行っていた動作が分からなくなってしまうのです。
≪対応方法≫
食べ方を忘れてしまった場合は、目の前で一緒に食べてあげるようにしましょう。このとき、食べ方が真似できるよう、食べている様子を見えるようにすることが大切です。
■体調が悪くて食事する気にならない
口内炎があったり入歯が合わなかったりなど、口の中の状態が悪いために食事したくなくなることがあります。他にも、便秘や風邪といった体調不良でも食事の意欲がなくなります。 体調が悪いと、不機嫌になり怒りっぽくなるため、食事させようとする行為は控えましょう。
≪対応方法≫
相手の表情や様子を見て「お口の中が痛みますか?」「お腹が痛いですか?」などの質問をしましょう。このときの質問は「はい」か「いいえ」で答えられるようなものにすることがポイントです。
■嚥下(えんげ)機能の低下
口に含んだ食べ物を飲み込むことを嚥下と言います。この機能が低下すると、飲み込むことができずに吐き出してしまったり、食べ物が気管に入ってしまう誤嚥のリスクを高めてしまったりします。
≪対応方法≫
食べ物の大きさを食べやすいサイズにしたり、固さを変えたりして、食べやすくします。
食事の具材を工夫しても、食べにくそうにしている場合は、ゼリー食などに変更しましょう。
無理に飲み込むと、気管に入って肺炎を起こしてしまう恐れがあるため注意が必要です。
また、嚥下力が低下した際は医師や専門家に相談してください。
■注意が他に逸れている
食事が用意されていても、食事の席につかずに徘徊してしまうことがあります。 食事よりも、ほかに大事なことがあるために食事を後回しにしてしまうのです。たとえば、自宅に帰りたいなどの帰宅願望によって徘徊してしまうことが多いです。
≪対応方法≫
食事を一緒に食べるようにしましょう。マンツーマンで対応すると食べてくれることがあります。食事の席から離れて徘徊してしまっている場合は、本人が満足するまで一緒に歩いてみて、気が済んだら改めて食事をおすすめするようにしましょう。
食事の介助のポイント
食事を促すときは、怒ったり急かしてはいけません。食事の時間が怖いものだと感じてしまう恐れがあります。
また、無理やり食べさせるという行為は誤嚥をおこしてしまう恐れがあるため、絶対にやってはいけません。
食事の介助をする際は、声を掛けたりボディータッチしたりしながら、明るく楽しく過ごせるようにすることが大切です

気持ちの沈みこみや、薬の副作用による眠気などでも食事を拒否することがあります。
いつも同じ原因で食事拒否をするとは限りません。しっかりと、現在の状況を観察して体調が悪いのか、食欲がないのかなど判断して対応することが大切ですよ。

記事監修:老人ホーム入居相談員(介護福祉士、社会福祉士、ホームヘルパー2級、宅地建物取引士、認知症サポーター)