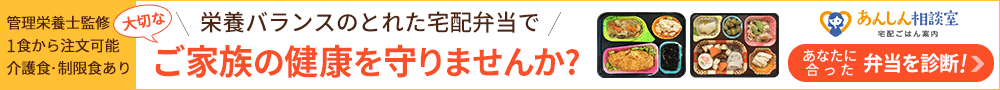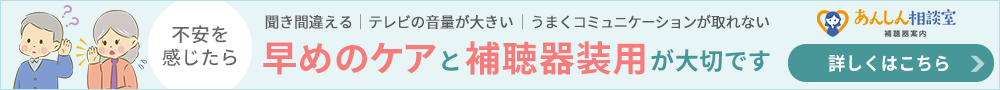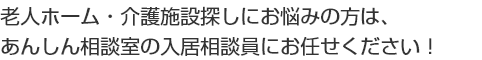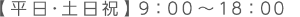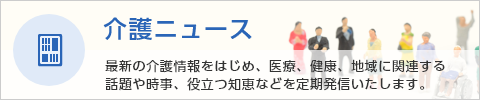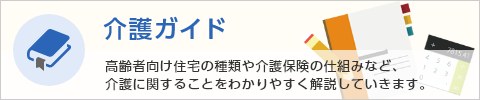介護施設で行われる【排泄ケア】とは何をすること?
2017.8.7

介護職員が利用者の生活を援助するうえで、食事ケアや入浴ケアと同じくらい大切なのが排泄ケア(トイレ介助)。では具体的に排泄ケアというのは、どういった介助をすることなのでしょうか?
また、排泄ケアの対応は施設の種類によって事情が異なりますので、その違いについても合わせて説明していきます。
そもそも排泄ケアってどんなこと?
そもそも排泄ケアってどんなこと?介護において排泄ケアは、基本中の基本。高齢で足腰が弱った人や寝たきりの人など、自力でトイレに行くことや日常的な排泄が困難になったとき、手助けや介護用具の利用で介助するのが排泄ケアです。
排泄ケアは実際のトイレで行う場合と、トイレまで距離がある際などポータブルトイレを使用してベッドの近くで行う場合があります。 トイレでの介助では、下着の上げ下げ、体をしっかり抱えての便座への腰掛けと立ち上げ、排泄後のお尻拭きなどを連動して行います。このとき健康状態をチェックするため排泄物の状態や皮膚の状態を確認します。
ポータブルトイレでは、ベッドからの立ち上げと便器への腰掛けを行い、それ以外は同様です。利用者にマヒがあれば体の動かし方やトイレの位置に注意します。
利用者の尊厳を傷つけないケアとは?
排泄は食事や睡眠と同じくらい重要なことです。しかし高齢になるにつれて排泄機能は少しずつ弱まるものですから、排泄ケアすることは生活介助の中でも不可欠です。
ただし、利用者の尊厳を損ねないことも忘れてはなりません。ポータブルトイレを利用する際にはカーテンや衝立などで仕切りを作ったり、自宅トイレでは排泄中ドアを閉めたりして、リラックスできる状態を作ります。介助の途中で相手を急かしたり、責めたりするような発言をすることも避けたいものです。
またおむつを使用するケースもありますが、あまり安易に利用すべきではありません。おむつの利用は高齢者の尊厳を傷つける場合もありますし、皮膚がかぶれやすくなったり尿意・便意を感じにくくなったりすることもあります。
おむつをなるべく使わない生活を指導するのも、広い意味で排泄ケアといえるでしょう。
施設によって方針はまちまちですので、確認しておきましょう。
サ高住で排泄ケアは受けられない?
では、介護施設では排泄ケアはどのように対応されているでしょう?
介護付き有料老人ホームでは、排泄介助を始め、食事・入浴・着替えなど、利用者の体に触れて行う介護サービス(身体介助)はもちろん対応可能です。基本サービスが日常そのものをサポートする生活援助である介護付き有料老人ホームならば、排泄が困難な人でも安心です。
対して、高齢者の暮らしをより安心かつ快適にするサービスを提供することが目的のサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)では、身体介助は基本的に訪問介護となります。スタッフが24時間常駐しないためトイレ介助も定時対応、おむつ着用となることが多いです。ただし施設によっては介護環境が整備されている場合もあります。
いずれにしましても、入居を決める際にはその施設が行う排泄ケアの質について事前に確認しておくと良いでしょう。

記事監修:老人ホーム入居相談員(介護福祉士、社会福祉士、ホームヘルパー2級、宅地建物取引士、認知症サポーター)