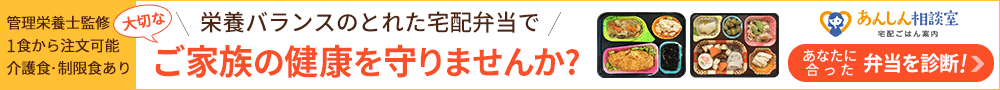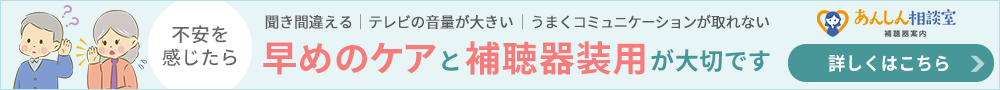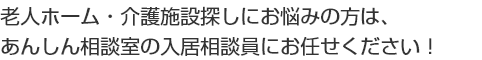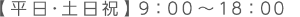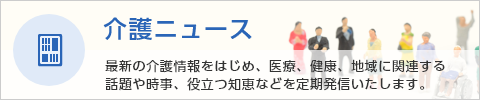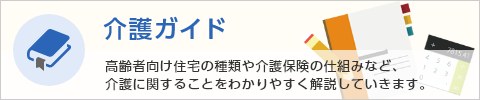認知症の方は睡眠障害になりやすい?その対策法とは
2017.5.12

年齢を重ねるとともに、睡眠の質は変化していきます。健康な高齢者の方でも眠りが浅くなったり、深夜に目が覚めてしまったりするようになります。
特に認知症の方は、睡眠の質が悪くなりやすいという特徴があるため注意が必要です。
ここでは認知症の方がなりやすい睡眠障害と、その対策方法についてご紹介します。
睡眠障害とは?
睡眠障害と聞くと、「なかなか寝付けない」「夜眠っていてもつい目が覚めてしまう」といった症状を思い浮かべる方もいるでしょう。
睡眠障害は、睡眠に何らかの形で問題があることを指します。このため【寝付けない・眠れない】だけが睡眠障害ではなく、他にもさまざまな症状があります。
睡眠障害になる原因には、生活環境の変化やストレス、精神的・身体的な病気など複数の要素が考えられます。
- ・昼間の強い眠気
- ・睡眠のリズムの乱れ
- ・睡眠中の病的な運動や行動(※2)
- ・夜間に何度も起きる中途覚醒 ・朝早く起きる早朝覚醒
- などの症状があらわれます。
※1 参照元:厚生労働省HP『睡眠障害』
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/03/s0331-3a.html
※2 睡眠中の運動・行動について
たとえば、睡眠中に四肢が勝手に動く周期性四肢運動障害や、睡眠中に夢体験と同じ行動をとるレム睡眠行動障害などが挙げられます。
認知症の睡眠障害
認知症の方は、同年代の方と比べても睡眠が浅いという特徴があり、さまざまな睡眠障害があらわれやすいと言われています。
重度の認知症の方は、1時間程度の短時間でも連続して眠ることができない方も多いです。
夜間の睡眠時間が減ったり質が落ちたりしてしまうと、日中の睡眠が増えて不規則な生活になり、さらに睡眠障害を悪化させてしまう場合があります。
認知症の方の中には、夕方から就寝時間までに徘徊・焦燥・興奮などの行動が増える「日没症候群」という症状があらわれる方がいます。これも睡眠の異常が関係していると考えられています。
睡眠を健康に保つには
認知症の方の睡眠の質を保ち、健康的な生活を維持するためには次のポイント(※3)を意識しましょう。
- ・温度や明るさなど、眠りやすいように就寝環境を整える
- ・午前中に日光を浴びる習慣をつける
- ・起床と就寝時間を整える
- ・昼寝を避ける(日中はベッドを使用しないようにする)
- ・運動する習慣をつける(できるだけ決まった時間で行い、就寝前の4時間は避ける)
- ・夕刻以降に水分を過剰摂取しないようにする
- ・「アルコール」「カフェイン」「ニコチン」の摂取を避ける
※3 参照元:厚生労働省提供のe-ヘルスネット『高齢者の睡眠』
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-02-004.html
【対策の注意点】
予定に合わせて生活を送ることは大切ですが“就寝時刻や睡眠時間にこだわりすぎないこと”も大切です。 「何時に眠らなければならない」と意識をし続けると、かえってストレスになってしまう恐れがあります。また「何時間寝なきゃいけない」という義務感も持たないようにしましょう。何時間眠れたかにかかわらず、毎日同じ時間に起きることを優先してください。

認知症の方の場合、睡眠障害は日中の行動に影響することも珍しくありません。
そしてその日中のトラブルや問題行動がストレスとなり、さらに睡眠障害を悪化させてしまう恐れもあります。
睡眠障害は、無理をせずに少しずつ生活習慣を見直して睡眠障害を予防、克服するようにしましょう。

記事監修:老人ホーム入居相談員(介護福祉士、社会福祉士、ホームヘルパー2級、宅地建物取引士、認知症サポーター)