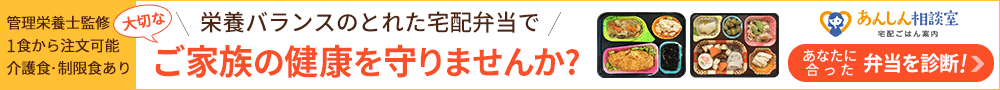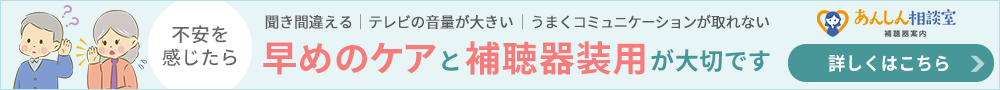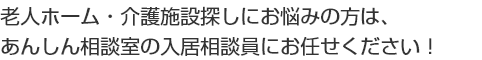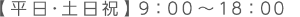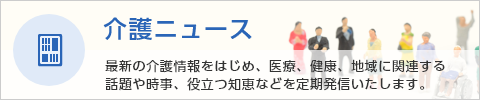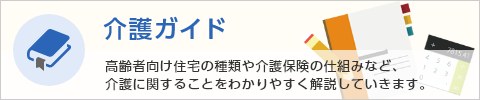長寿の記念「還暦」そもそも由来って?どうして祝う?
2017.4.21

長寿のお祝いの一つに還暦(かんれき)がありますね。60歳になった男性が頭に赤い頭巾を乗せ、赤いちゃんちゃんこを羽織った姿で、家族から「おじいちゃん、還暦おめでとう!」と祝福を受ける…そんな光景、かつてテレビドラマの一シーンなどで時折見かけました。
今回は、そんな還暦の由来などについて詳しく説明します。
還暦を祝福するのは「60歳で赤ちゃんに還る」ため
還暦は一般的に満60歳のお祝いという印象がありますが、正確には数え年61歳(誕生年+60年)のことです。数え年で年齢を数えることは現在あまりありませんが、以前は1月1日をもって「1つ歳を重ねた」と考えていたためこのように判断されていました。ただし現在では満60歳でお祝いをすることが一般的になっています。
ところで、なぜ還暦はおめでたいのでしょう?
還暦は別名「本卦還り(ほんけがえり)」とも呼ばれます。これは中国の暦「十干十二支(じっかんじゅうにし)」の数え方に由来した呼び方です。
普段私たちは、干支というと十二支(子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥)のことを思い浮かべますが、本来の干支はこれに十干(甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)を組み合わせた計60種類の暦のことです。有名な「丙午(ひのえうま)」などもその一つですね。
目指すは120歳の大還暦?節目のいろいろ
還暦の満60歳以外で長寿のお祝いを行う節目として知られているのは、70歳の古希、77歳の喜寿、88歳の米寿、90歳の卒寿、99歳の白寿などです。他にも、100歳を紀寿または百寿、108歳を茶寿、111歳を皇寿と呼びます。
さらに、還暦の倍にあたる120歳のことを大還暦と呼びます。本卦還りを二度するとは信じられないほどの長命ですが、記録によると世界の最高齢記録は122歳だったそうですから、平均寿命が今なお伸び続ける世界の長寿国・日本にとって、大還暦はいずれ一つの目標になるかもしれませんね。
「健康で長生き」がなによりハッピー!
当欄では以前、平均寿命と健康寿命の違いについて説明しました。詳しくは過去記事「健康寿命という考え知っている?健康管理ができていない方へ」を参照してください。
2013年のデータによると、日本人の平均寿命は男性80.21歳、女性86.61歳。これに対して健康寿命の平均は男性71.19歳、女性は74.21歳です。健康寿命のポイントである「健康上問題なく日常生活が過ごせる期間」に照準を置いて考えると、ここに現れた「男性9歳、女性12歳」の差の意味は分かりやすいでしょう。すなわち、男性は平均寿命の晩年9年間、女性は晩年12年間以上、健康上何らかの問題を抱えた生活を過ごしているのです。
せっかく長生きしてもこれではもったいないですよね。
還暦を超えてからも健康に、楽しい人生を送りましょう!

記事監修:老人ホーム入居相談員(介護福祉士、社会福祉士、ホームヘルパー2級、宅地建物取引士、認知症サポーター)