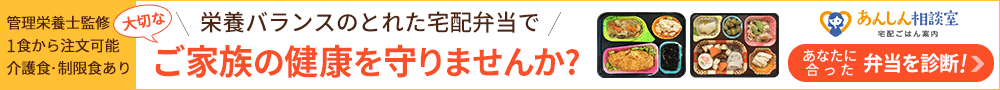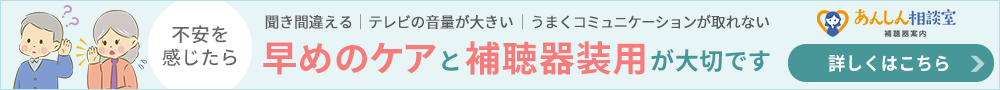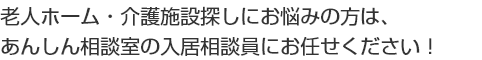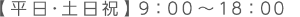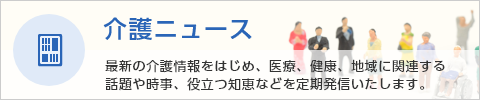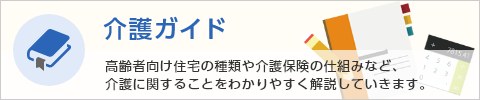サービス介助士の仕事内容とは?ヘルパーとの違い
2017.3.31

「サービス介助士」という高齢者や障害者をサポートする上で活用できる資格が、お客様との交流が多いサービス業から最近注目されつつあります。
サービス介助士という名前を知っていても、仕事内容や役割を知っている方は多くないかもしれません。
今回は、サービス介助士が求められる理由と仕事内容、ホームヘルパーとの違いについてご紹介していきます。
サービス介助士のニーズが高まる日本
サービス介助士は、高齢者の人口の割合が大きくなってきた日本において、高齢者や障害者をサポートするために、需要が高まりつつある資格です。
たとえば街中で困った高齢者や障害者を見かけたときに「助けてあげたい」と思っても、実際に「どのように介助すればいいのか」分からずに不安になってしまうもの。その不安の原因は知識や技術がないことからくる自信のなさにあると考えられます。
そこで、いつどんなときでも困っている人を咄嗟に助けられる「知識」と「技術」の習得を目的とするサービス介助士という資格が設けられました。
「サービス介助士」を活かせる仕事
サービス介助士の仕事は、障害者や高齢者が安心して公共施設などを利用できるようにサポートすることです。主に車いすを利用している方、視覚に障害がある方、聴覚に障害がある方の介助を行います。 「サービス介助士」の資格はあくまで「介助ができる」「介助に関する知識がある」ということの証です。決して資格を取得していなければ、やってはいけないという仕事ではありません。
サービス介助士という資格を保有している人が「駅などの交通機関」「公民館などの公共施設」「スーパーなどの店舗」にいることで、高齢者や障害者が安心して利用できるようになります。
お客様とコミュニケーションを多くとるような企業や場所で、この資格は大いに活用できるでしょう。
ホームヘルパーとの違い
サービス介助士と混同されやすい仕事のひとつにホームヘルパーがあります。
ホームヘルパーの仕事は、高齢者や障害者の家を訪問して、入浴や食事などの介護や家事サービスといったホームヘルプ事業を行うことです。
一方でサービス介助士は、比較的元気で外出可能な高齢者・障害者に対し、おもてなしの心を持って迎え入れて介助技術を活かしたサポートを行います。“介護”よりも“介助”に重きを置いているため、食事や入浴などの介護技術を必要としない人たちの日常の一部をサポートします。
サービス介助士に求められる役割
サービス介助士の役割は、単に介助技術を身に付けるだけでなく「おもてなしを行う」点にあります。特に高齢者や障害者に対する適切なサポート、また当事者目線での職場の改善といった役割を求められることが多いです。
一般企業などで働く場合には、お客さまからの評価や信頼関係の構築につながると期待されています。

サービス介助士の資格を取得することで、知識や技術に自信がつくため、高齢者・障害者に適切でスムーズな介助を行うことができます。今後はサービス介助士の資格保有者を必要とする一般企業は増えてくることが予想されます。
公共施設においてバリアフリー化が進んでいるものの、高齢者や障害者が不便だと感じる施設も少なくないと言われています。
今後、そうした施設にサービス介助士の取得者が配置されることで、高齢者や障害者に対する適切なサービスが増え、利用するお客様の安心につながっていくことでしょう。
介護とおもてなしの心を両立したサービス介助士という資格からは目が離せません。

記事監修:老人ホーム入居相談員(介護福祉士、社会福祉士、ホームヘルパー2級、宅地建物取引士、認知症サポーター)